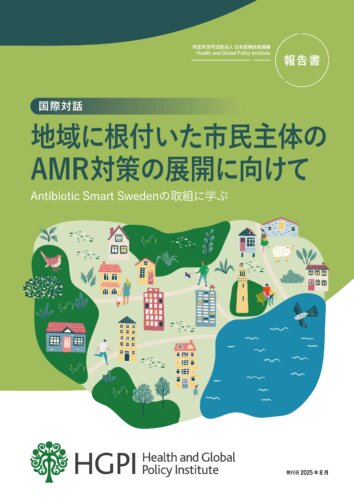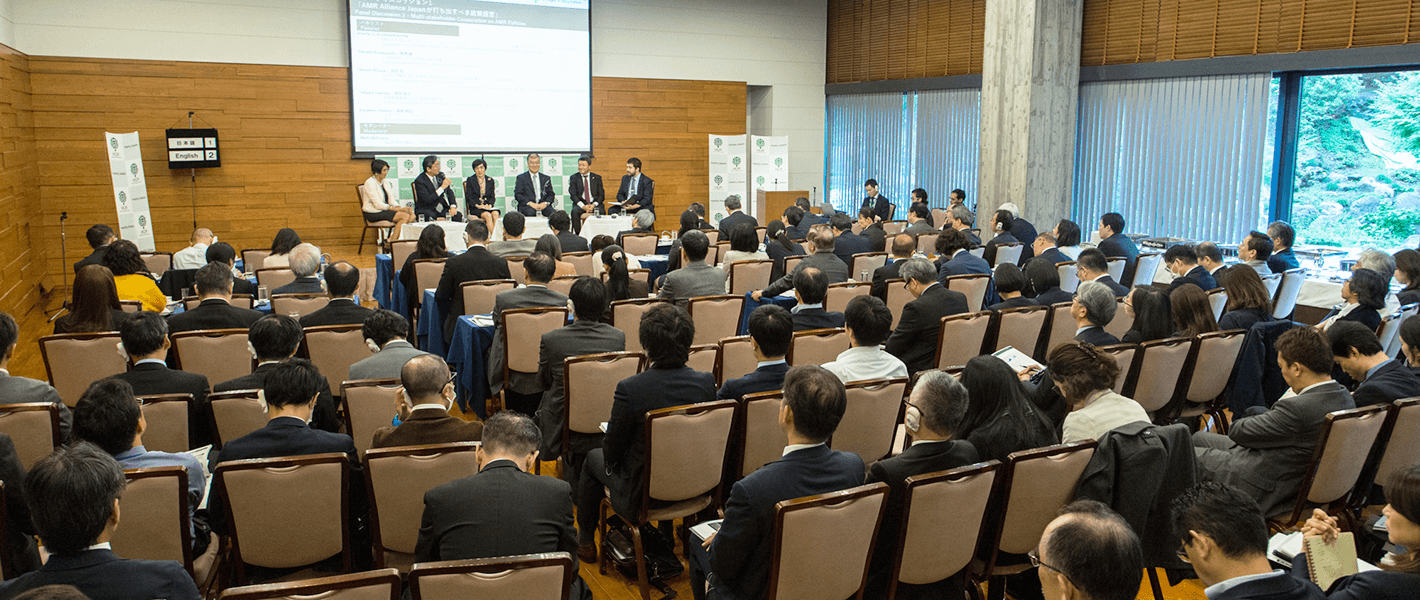【論点整理】国際対話「地域に根付いた市民主体のAMR対策の展開に向けて-Antibiotic Smart Swedenの取組に学ぶ-」(2025年8月29日)
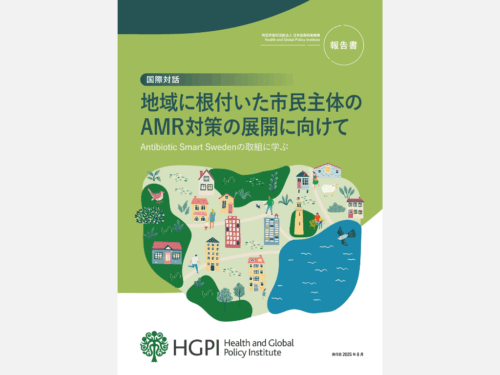 日本医療政策機構は、報告書「地域に根付いた市民主体のAMR対策の展開に向けて-Antibiotic Smart Swedenの取組に学ぶ-」を公表いたしました。
日本医療政策機構は、報告書「地域に根付いた市民主体のAMR対策の展開に向けて-Antibiotic Smart Swedenの取組に学ぶ-」を公表いたしました。
薬剤耐性(AMR: Antimicrobial Resistance)は、公衆衛生・国際保健上の深刻な課題であり、EUやG7等の国際社会の場でも重要な課題として位置づけられています。また、AMRは人間・動物・食品・環境にまたがる複雑な課題であり、その解決には医療機関や高齢者施設、教育機関、上下水道施設、農蓄水産業施設等、ワンヘルス・アプローチに基づいた多様な分野の連携が欠かせません。
ただし、こうした施設や制度は市民の日常生活と密接に結びついており、実際の活動は地域の人口動態や歴史、地場産業等の地域固有の特性を色濃く反映します。そのため、効果的かつ持続可能なAMR対策を推し進めるためには、多様な関係者の賛同と協力を得ながら、地域に根差した仕組みを構築することが求められます。
参考事例の1つがスウェーデンで省庁横断的に立ち上がった「Antibiotic Smart Sweden」という取り組みです。同取り組みでは、複数の自治体や地域が参画して、AMR対策における分野横断的な連携を地域に根付いた形で展開してきました。
そこで当機構では、スウェーデン関係者をお招きし、2024年10月25日に国際対話「地域に根付いた市民主体のAMR対策の展開に向けて-Antibiotic Smart Swedenの取組に学ぶ-」を開催いたしました。
報告書では、国際対話での議論をもとに、地域に根付いたAMR対策の在り方や実現に向けた方向性を整理しました。また、両国の自治体による取り組み事例として、スウェーデンのタヌム市、日本の福岡県、姫路市の実践例を取りまとめています。
詳細は末尾のPDFをご覧ください。
論点1
AMR対策には、幅広い分野の知見と多様な組織・団体の協力が不可欠である。分野横断的な連携を促進するには、既存のネットワークや組織の専門性と特徴を活かした連携体制を構築する必要がある。
論点2
地方自治体は、行政構造の特徴を活かしたAMR対策の推進が求められる。基礎自治体(市町村)は、住民との近接性を強みにして、啓発・学修支援を軸に地域に根ざした取り組みの展開が期待される。広域自治体(都道府県)は、基礎自治体間の調整・支援を行い、分野横断的な研究やAMR対策基盤の整備に取り組むことが期待される。
論点3
国は、広域的かつ全国規模のAMR対策を主導する必要がある。また、地方自治体間の連携を促進することで、地域の自主性を尊重しながら、多様化する社会ニーズに対応することが期待される。
論点4
AMR対策の啓発・学修支援は、認知・理解・行動変容の段階を踏まえて実施する必要がある。
論点5
行政区域や分野を越えた統合的なサーベイランス体制の構築が必要である。実効性のあるサーベイランス体制には、国、都道府県、市町村の役割分担とワンヘルスの視点に基づく分野横断的な協力が不可欠である。