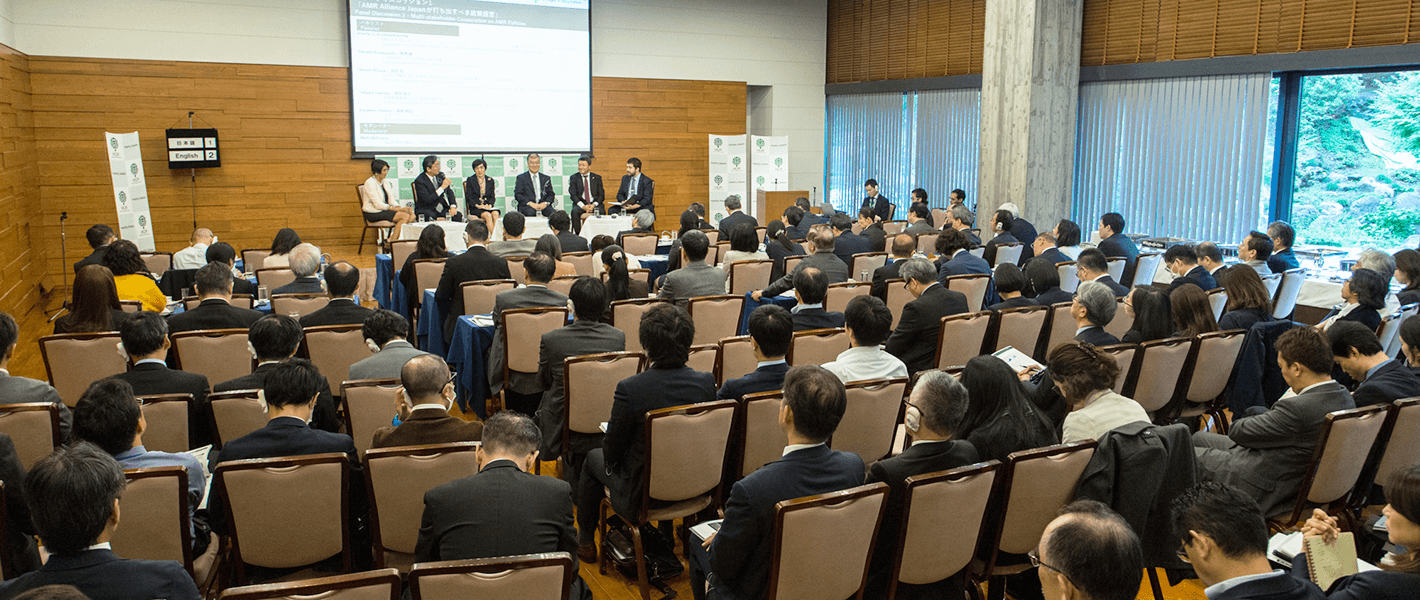【当事者の声】紛争地域における薬剤耐性対策:ガザ地区での診療から見た紛争地域における薬剤耐性対策の課題と新たな視点(2025年6月10日)
鵜川 竜也氏
国境なき医師団 医師
AMRは人類が直面している最も深刻な健康上の脅威の一つといわれており、日本を含む先進国では基本的な衛生管理や院内感染対策、高度な医療設備等を基盤としたAMR対策が展開されています。一方、紛争地域では医療制度の崩壊により、AMR対策が極めて困難になっています。紛争地域では、目の前にある命を救うための治療が何より優先され、AMR対策を含む感染症対策の優先順位が下がりがちです。しかし、まさにそのAMRの影響で、治療の選択肢が限られることがあります。加えて、耐性菌は国境を越えて広がるため、国際社会で対策を講じることが不可欠です。そのため、グローバル化が進む現代において、海外諸国のAMR対策の状況は日本の私たちも注視すべき重要な課題です。
 AMRアライアンス・ジャパン(事務局:日本医療政策機構)では、薬剤耐性対策の政策推進に向けて、国内外の薬剤耐性(AMR: Antimicrobial Resistance)の患者・当事者と共に活動してきました。活動の一環として、2021年からAMR対策に関わる患者・当事者や市民の声を集めています。今回は、紛争地域におけるAMR問題の実態を理解するため、AMR対策を紛争地域で行う当事者として国境なき医師団(MSF: Médecins Sans Frontières)において、2023年4月から7か月間ガザ地区で医師の立場から医療援助活動に従事した鵜川竜也氏に話を伺いました。同地域では、国境なき医師団をはじめ、国際的な医療援助団体による医療提供が行われているものの、AMRに関連する様々な課題が存在していることが明らかになっています。
AMRアライアンス・ジャパン(事務局:日本医療政策機構)では、薬剤耐性対策の政策推進に向けて、国内外の薬剤耐性(AMR: Antimicrobial Resistance)の患者・当事者と共に活動してきました。活動の一環として、2021年からAMR対策に関わる患者・当事者や市民の声を集めています。今回は、紛争地域におけるAMR問題の実態を理解するため、AMR対策を紛争地域で行う当事者として国境なき医師団(MSF: Médecins Sans Frontières)において、2023年4月から7か月間ガザ地区で医師の立場から医療援助活動に従事した鵜川竜也氏に話を伺いました。同地域では、国境なき医師団をはじめ、国際的な医療援助団体による医療提供が行われているものの、AMRに関連する様々な課題が存在していることが明らかになっています。
(インタビューに答える鵜川医師)
目次:
臨床医と検査技師をつなぐ感染症専門医の役割
紛争地域の感染症管理では、感染症専門医が臨床医と検査技師の橋渡し役として重要な役割を果たします。私はガザ地区で活動している際、抗菌薬専門医(Antibiotic Doctor)として手足再建手術プロジェクトに参画していました。紛争地域ではその性質上、爆撃等による外傷や銃創等による外科的治療が頻繁に行われ、こうした状況下での適切な感染管理が必要となります。そのため、私は検査技師とともに検査結果の妥当性を評価し、外科医・内科医を含む臨床医と共に最適な抗生物質を選定・使用することを支援していました。しかし、検査技師は現場の医療状況を把握するのが難しく、一方で臨床医は検査室の詳細な運営を知らないことが多いため、両者をつなぐ専門家が必要となります。日本の医療現場でも臨床医と検査技師とのコミュニケーションは限られていますが、紛争地域でもこの連携基盤の構築が重要です。
MSFのプロジェクトでは、リファレンスマネージャーと呼ばれる専門家が検査室の立ち上げから関わり、検査と臨床をつなぐ役割を担っています。世界標準の検査手法を理解し、限られた医療資源のなかで適切な抗菌薬の選択を支援しています。紛争が激化すると、検査室の運営はさらに困難になり、臨床検査技師等が出勤できなくなることもありましたが、それまでに蓄積したデータを活用して、抗菌薬の選択や治療方針を決定していました。こうした経験は、平時の感染症対策の重要性を再認識させるものでもあります。
紛争地域における周術期管理の課題
現地の医療機関では一日に4名から5名程度の外科手術が行われます。病棟では常に20名前後の周術期の患者を受け入れています。こうした環境での最大の課題の一つが周術期の感染症管理です。紛争地域では、適切な周術期管理、特に感染症対策に必要な医療資源が著しく不足しています。例えば、周術期管理においては適切な細菌検査が欠かせませんが、検査に必要な試薬が十分に確保できないため、感染症の原因菌を正確に特定することが困難です。
さらに、検査機器の不足も深刻な問題です。日本の医療機関で細菌の薬剤感受性試験(ある細菌に特定の抗菌薬が効果を持つかどうかの試験)を行う場合、その方法は微量液体希釈法という機械化された方法を用いることが一般的です。しかし、ガザではそうした検査機器がほとんど存在しないため、ディスク拡散法といわれる手作業で検査の作業を行わなければいけないこともありました。この方法は時間と労力を要し、結果の精度も機械化された方法に比べて劣ることがあります。
その結果、感染症の病原菌を特定できず、適切な抗菌薬の選択も困難になり、術後感染症の増加につながりました。例えば、術後の骨髄炎など、日本では経験することが少ない症例も多くみられます。特に、銃創患者などの重症例では、複数回の抗菌薬使用により使用可能な薬剤が限られ、日本では一般的に使用されないような抗菌薬を使用せざるを得ないケースもありました。
厳しい環境ながら、現地の医療施設には臨床検査技師が配置されており、現地スタッフの学習意欲は高いです。医療記録の管理は紙カルテが主流で患者の治療歴の把握が難しいなど課題はありますが、MSFの支援の下で新しい検査手法の導入にも積極的に取り組むなど、前向きな姿勢が見られる点は希望につながっています。
抗菌薬が手軽に入手できることの是非
一方、医療施設から出て、市街地での状況を見てみると、紛争地域や中低所得国では、処方箋なしで抗菌薬を購入できる薬局が多く、AMR対策において深刻な問題となっています。抗菌薬の適正使用がされなければ、耐性菌の発生が加速し、治療の選択肢が減少してしまいます。AMR対策としては抗菌薬の適正使用が欠かせませんが、この環境がAMRの発生を助長していることは明らかです。
そこで、週に1回ほどのペースで地域の薬剤師向けに勉強会を実施し、不適切な抗菌薬販売の防止に向けて活動していました。ただ、現場の薬剤師の努力だけでは限界があると感じます。市民へのAMR教育とともに、現地の薬剤販売システムへの改革など、より包括的な取り組みが必要です。しかし、適切な医療へのアクセスが限られた紛争地域や低中所得国の市民にとって、抗菌薬の販売を厳しく制限することは生死に直結する可能性があるため、慎重な対策が必要だと考えています。
文化的な配慮と感染症対策
紛争地域、主にイスラム圏では、ラマダン期間中の投薬など、文化的・宗教的な配慮が治療方針に影響を与える場合があります。例えば、抗菌薬の多くは腎臓への負担(腎毒性)が他の薬剤よりも大きく、水分制限のあるラマダン期間中の投与は慎重に計画する必要がありました。私も現地スタッフと協力し、脱水や腎機能低下のリスクを考慮しながら、投薬計画を調整しました。文化的背景を尊重することはAMR対策を促進し、実効性を高めるためにも不可欠な姿勢だと思います。
最後に~紛争地域のAMR対策を考えることは持続可能な医療の形を考えること~
AMR対策では、感染症診療の充実に向けた医療・検査体制の整備が重要です。紛争地域でも適切なAMR対策実施するためには、検査機器や治療薬の供給のみならず、臨床検査技師と臨床医の橋渡しを行う感染症医の配置など、人的・物的両面の支援が求められます。また、薬剤師によるAMR対策の推進や、地域住民への啓発学修支援を通じて、抗菌薬の適正使用を促す取り組みも重要でした。
実は、こうした課題の多くは、紛争地域のみならず日本を含む先進国にも共通します。現代のAMR対策は100年前に開発された抗菌薬というイノベーションを通して、各国・地域で暮らす市民が医療の持続可能性をどのように確保するかという新たな挑戦なのかもしれません。
薬剤耐性菌に関する症例報告
■第1回「キャンディン系抗真菌薬をブレイクスルーした播種性糸状菌感染症」
冲中 敬二(国立がん研究センター東病院・総合内科、中央病院・造血幹細胞移植科(併任)、感染制御室室長)
■第2回「耐性菌の影響は生まれたばかりの乳児にも!耐性菌による尿路感染症の生後5か月男児」
笠井正志(兵庫県立こども病院 感染症内科 部長)
大竹正悟(兵庫県立こども病院感染症内科 フェロー)
■第3回「カンジダ血症ではルーチンの眼科的精査が必要!」
植田 貴史(兵庫医科大学病院 感染制御部)
■第4回「MRSA感染症治療における適正使用の重要性。リファンピシン単剤治療による耐性誘導に注意。」
茂見 茜里(鹿児島大学病院 薬剤部/感染制御部)
■第5回「ピペラシリン/タゾバクタムとバンコマイシンの併用により腎障害発現リスクが上昇」
鏡 圭介(北海道大学病院薬剤部)
菅原 満(北海道大学病院薬剤部/北海道大学大学院薬学研究院医療薬学部門医療薬学分野薬物動態解析学研究室)
■第6回「リネゾリドの血中濃度モニタリングにより血小板減少を回避-難治性化膿性椎体椎間板炎でリネゾリドの長期投与が可能となり治療が奏功-」
鏡 圭介(北海道大学病院薬剤部)
菅原 満(北海道大学病院薬剤部/北海道大学大学院薬学研究院医療薬学部門医療薬学分野薬物動態解析学研究室)
■第7回 当事者の声「薬剤耐性菌の問題に関心をもち、抗菌薬の適切な使用を推進する医療従事者が増えることを願っています」
伊東 幸子(AMRアライアンス・ジャパン サポーター/肺NTM(Nontuberculous Mycobacteria:非結核性抗酸菌)症 当事者)
■第8回 「安全性だけではないTDMの活用法 ~有効性確保のためにできること~」
桝田 浩司(学校法人国際医療福祉大学成田病院 薬剤部 副主任)
池田 賢二(国際医療福祉大学 成田病院薬剤部責任者/薬学部准教授)
■第9回 当事者の声「眼科疾患と薬剤耐性の経験」
丸山 純一(元 駐セルビア日本大使)