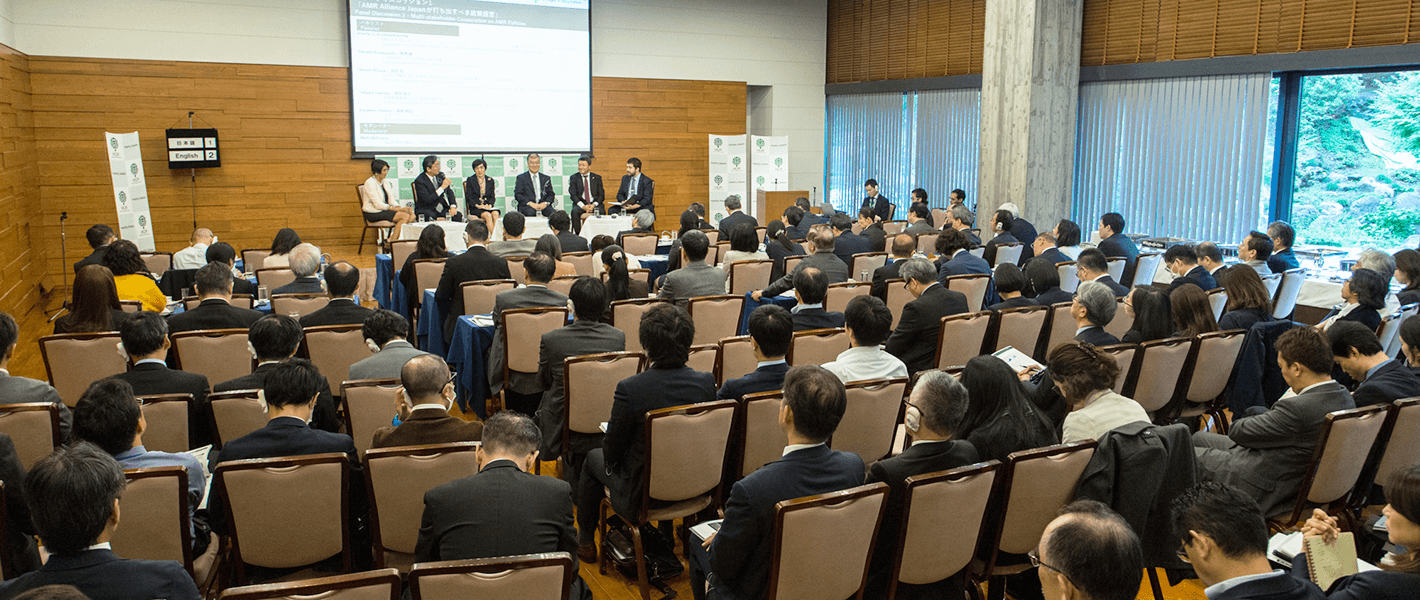丸山 純一氏
元 駐セルビア日本大使
 今回は、継続的に眼科治療を受けている丸山純一氏より、長期間に及ぶ抗菌薬使用が薬剤耐性を誘導した結果、将来の治療選択肢に影響を与える可能性について語っていただきました。特に現在、唯一視野が保たれている左眼の白内障手術に対する不安と、薬剤耐性という課題の身近さについて共有いただきました。
今回は、継続的に眼科治療を受けている丸山純一氏より、長期間に及ぶ抗菌薬使用が薬剤耐性を誘導した結果、将来の治療選択肢に影響を与える可能性について語っていただきました。特に現在、唯一視野が保たれている左眼の白内障手術に対する不安と、薬剤耐性という課題の身近さについて共有いただきました。
(日本医療政策機構 国際シンポジウムで自身の体験について講演する丸山氏。)
目次:
はじめに
本稿では、薬剤耐性の問題に直面している一人の患者として、私の経験を共有させていただきます。薬剤耐性と聞くと少し難しく思われるかもしれませんが、実は誰もが日常生活で直面する可能性があります。薬剤耐性の身近さを実感していただき、薬剤耐性対策の重要性について読者の皆様と一緒に考える機会となれば幸いです。
(1)眼の外傷とその治療
私は若い頃の事故により、右眼にガラス片が入り視野の一部が失われました。もちろんすぐに手術を行いましたが、眼球内にはガラス片の一部が残存しています。ガラス片は人間の身体にとって一種の異物であり、そこから感染症が発生しやすくなります。そのため、継続的に医療機関で様子を見る必要がありました。私は長年ニューキノロン系抗菌薬の1つであるレボフロキサシンという点眼薬を使用して治療を続けてきました。定期的な経過観察を行いながら、3ヶ月に1回の診察を継続しています。
ところで、私の症例は医学的に興味深いケースだったようで、担当医以外にも複数の医師が交代で診察に来る場合が少なくありませんでした。ときには実験台として観察されているような気分になり、精神的にも負担がありました。患者として治療を受ける立場でありながら、自分が医療従事者の医学的知見を深めるための対象としても認識されていることに複雑な心境を抱えていました。
(2)薬剤耐性の出現と治療の変更
そのようななかでも、医師の指示の下で抗菌薬を適切に使用してきたこともあり、幸い大きな感染症に見舞われることはありませんでした。しかし、治療を継続する中で、これまで使用していた点眼薬の効果が低下しているような感覚がありました。そこで医療機関で検査を受けたところ、いつの間にかレボフロキサシンへの薬剤耐性が出現していたことがわかりました。その時点から私はレボフロキサシンが使えなくなり、同じニューキノロン系抗菌薬のトスフロキサシンに点眼薬を変更せざるを得なくなりました。さらに、これ以上薬剤耐性菌を出現させないように、新しい点眼薬は必要最小限の使用に抑えるように医師から指示を受けました。ただ、当時の私はこの事態をあまり深刻に受け止めてはいませんでした。
(3)網膜手術と白内障への対応
2024年、私は右眼網膜の手術を2度にわたり受けることになりました。この時、既に薬剤耐性を持っていることについて事前に医師に伝え、適切な対応をしていただいたことで、問題なく手術を終えることができました。今回の網膜手術では、白内障の手術も同時に行いました。網膜の手術を行うと白内障が進行しやすくなるため、多くの患者が2つの手術を同時に受けるそうで、一般的な対応のようです。
しかし、私にとって現在の本当の課題は左眼の状況です。唯一視野が保たれている左眼でも白内障が進行しており、いずれ手術が必要になります。右眼は動かず、視野も半分欠けているため、左眼は私の生命線です。そのため、左眼の白内障手術に対する恐怖心が依然として残っています。過去に薬剤耐性を経験したことで、手術の際に使用できる抗菌薬が限られてしまうかもしれません。感染予防の抗菌薬が十分に使用できなければ、唯一視力が残る左眼の治療に影響が出る可能性があります。この現実に不安を感じています。通常なら当たり前に使えるはずの薬が使えないかもしれないという状況は、患者にとって非常に切実な問題です。
※本記事は2023年2月28日に開催しましたAMR特別シンポジウム「薬剤耐性対策推進に求められる次の打ち手 G7、国連総会ハイレベル会合を見据えたマルチステークホルダー連携」(主催:日本医療政策機構(HGPI)、協力:駐日英国大使館、英国保健省、欧州復興開発銀行(EBRD))でのご講演を元に、追加でインタビューを行い作成いたしました。
薬剤耐性菌に関する症例報告
■第1回「キャンディン系抗真菌薬をブレイクスルーした播種性糸状菌感染症」
冲中 敬二(国立がん研究センター東病院・総合内科、中央病院・造血幹細胞移植科(併任)、感染制御室室長)
■第2回「耐性菌の影響は生まれたばかりの乳児にも!耐性菌による尿路感染症の生後5か月男児」
笠井正志(兵庫県立こども病院 感染症内科 部長)
大竹正悟(兵庫県立こども病院感染症内科 フェロー)
■第3回「カンジダ血症ではルーチンの眼科的精査が必要!」
植田 貴史(兵庫医科大学病院 感染制御部)
■第4回「MRSA感染症治療における適正使用の重要性。リファンピシン単剤治療による耐性誘導に注意。」
茂見 茜里(鹿児島大学病院 薬剤部/感染制御部)
■第5回「ピペラシリン/タゾバクタムとバンコマイシンの併用により腎障害発現リスクが上昇」
鏡 圭介(北海道大学病院薬剤部)
菅原 満(北海道大学病院薬剤部/北海道大学大学院薬学研究院医療薬学部門医療薬学分野薬物動態解析学研究室)
■第6回「リネゾリドの血中濃度モニタリングにより血小板減少を回避-難治性化膿性椎体椎間板炎でリネゾリドの長期投与が可能となり治療が奏功-」
鏡 圭介(北海道大学病院薬剤部)
菅原 満(北海道大学病院薬剤部/北海道大学大学院薬学研究院医療薬学部門医療薬学分野薬物動態解析学研究室)
■第7回 当事者の声「薬剤耐性菌の問題に関心をもち、抗菌薬の適切な使用を推進する医療従事者が増えることを願っています」
伊東 幸子(AMRアライアンス・ジャパン サポーター/肺NTM(Nontuberculous Mycobacteria:非結核性抗酸菌)症 当事者)
■第8回 「安全性だけではないTDMの活用法 ~有効性確保のためにできること~」
桝田 浩司(学校法人国際医療福祉大学成田病院 薬剤部 副主任)
池田 賢二(国際医療福祉大学 成田病院薬剤部責任者/薬学部准教授)